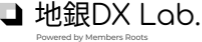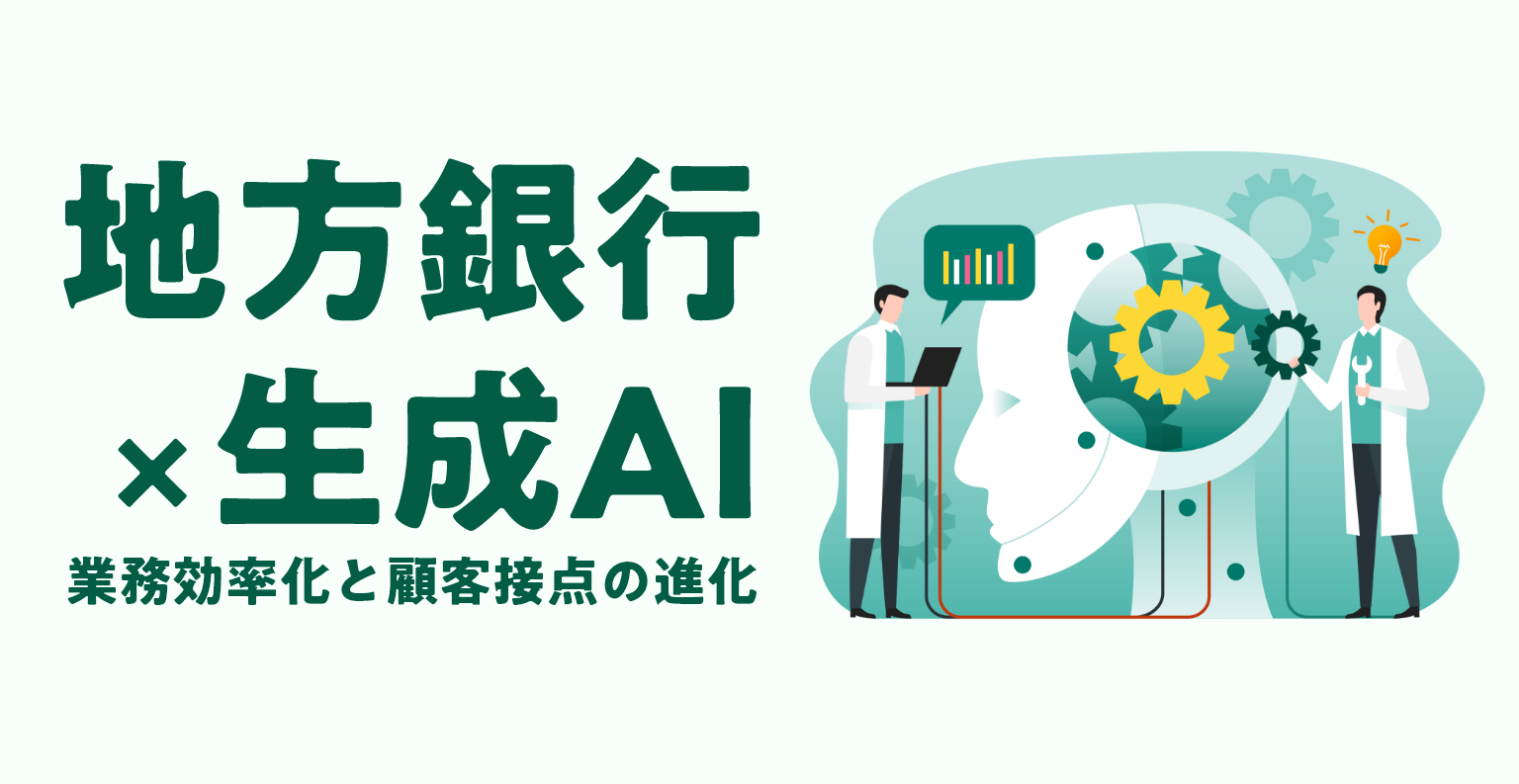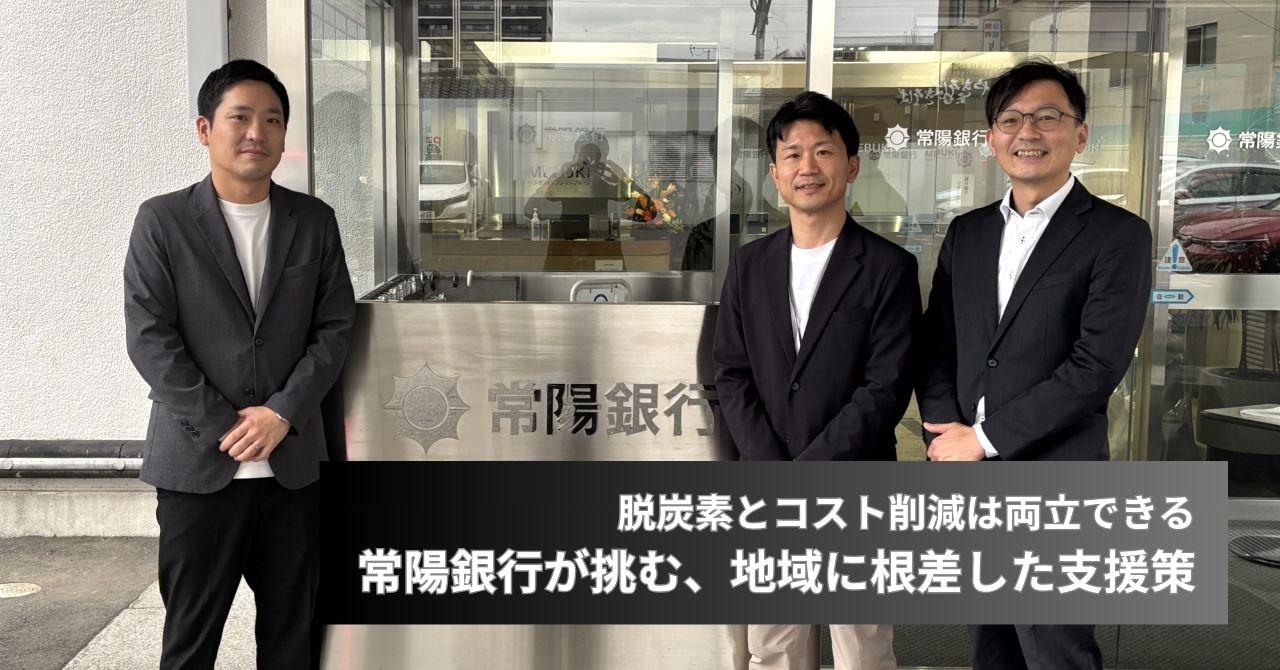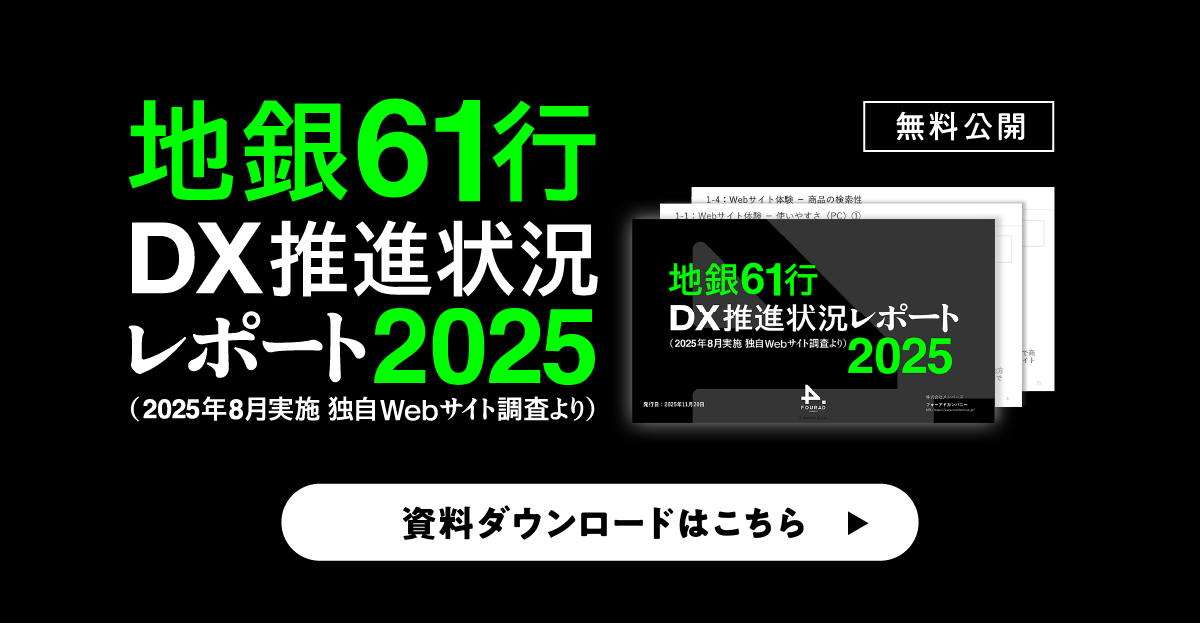生成AIが地銀にもたらす新たな可能性
2025年現在、地方銀行における生成AIの導入が急速に進んでいます。日本銀行の調査によれば、金融機関の約3割が生成AIを既に利用しており、試行中を含めると約6割、さらに試行・利用を検討している先を含めると約8割に達しています(出典:日本銀行 金融システムレポート 2024年10月21日)。
主な利用目的は業務効率化やコスト削減であり、文書作成の補助やシステム開発・運行管理などの分野で活用されています。
業務効率化への取り組み
地方銀行では、生成AIを活用した業務の省力化や質の向上に向けた実証が活発化しています。
- 北陸銀行・北海道銀行は、問い合わせ対応や文書作成、プログラム作成などに生成AIを活用し、ユースケースを精査する実証を進行中(出典:IT Leaders 2025年2月)。
- ソフトバンクは、地方銀行10行以上に対し、稟議策定支援や業務文書作成における生成AI活用の支援を提供。行内規定の照会や社内教育体制の構築も支援(出典:ニッキンオンライン 2025年1月)。
- 栃木銀行は、生成AI「GaiXer」を用いて議事録要約や文案作成業務を効率化(出典:Fixer公式 2024年12月)。
- 群馬銀行は、生成AIを活用した融資審査支援を実証。過去データの検索や判断の補助に活用(出典:PR TIMES 2024年12月)。
顧客接点の進化
生成AIの導入は、地銀の「顔」である顧客接点にも影響を与え始めています。
- 静岡銀行は、Snowflakeおよびブレインパッドと共同で、生成AIチャットボットを開発。顧客情報を活用した提案で営業の高度化を図る(出典:ブレインパッド 2024年10月)。
- 紀陽銀行は、生成AIを用いたFAQ自動応答機能を活用したコンタクトセンターの業務効率化を進行(出典:ニッキン 2024年12月18日)。
- 山陰合同銀行は、生成AIチャットボットを導入し、営業時間外の問い合わせ対応を可能に(出典:山陰合同銀行 2023年12月)。
今後の展望と課題
生成AIの利活用は、単なる省力化を超えて、地方銀行が地域金融機関としての役割を果たすうえでの重要な鍵となりつつあります。一方で、誤情報リスク、情報漏洩、利用ガイドラインの未整備といった課題も残ります。
日本銀行のレポートによると、多くの金融機関で「出力内容の正確性の検証」「業務適用に向けたルール整備」「行内教育」が今後の優先課題とされています(出典:日本銀行 金融システムレポート 2024年10月)。
地方銀行が生成AIを取り入れる際は、「地域密着」という地銀ならではの価値と、先進技術をいかに調和させるかが鍵となります。生成AIが本質的な業務改革と顧客体験の革新につながるかどうかは、今後の地銀DXを左右する重要な論点となっていくでしょう。
※この記事は2025年4月時点の情報をもとに構成されています。