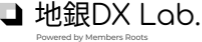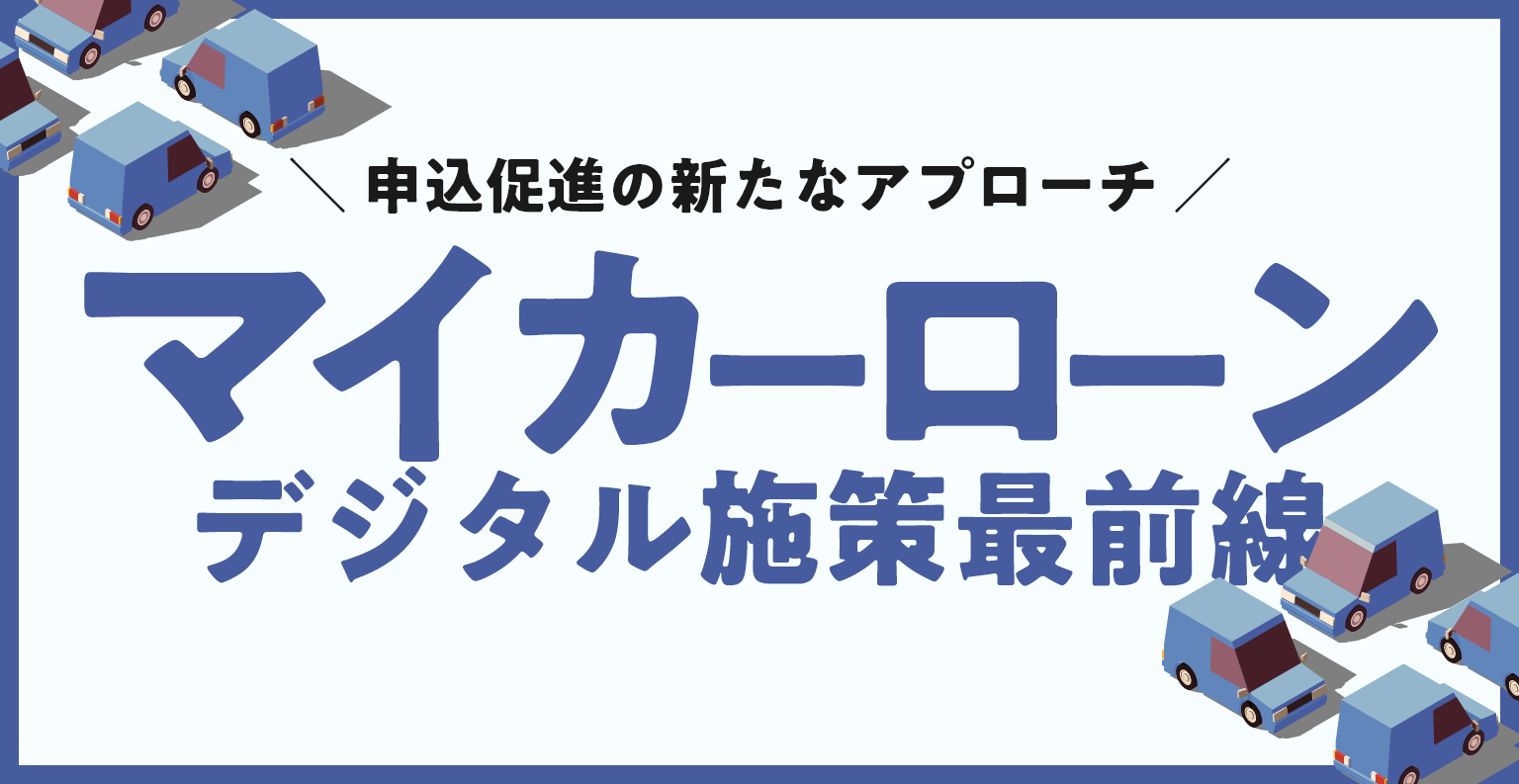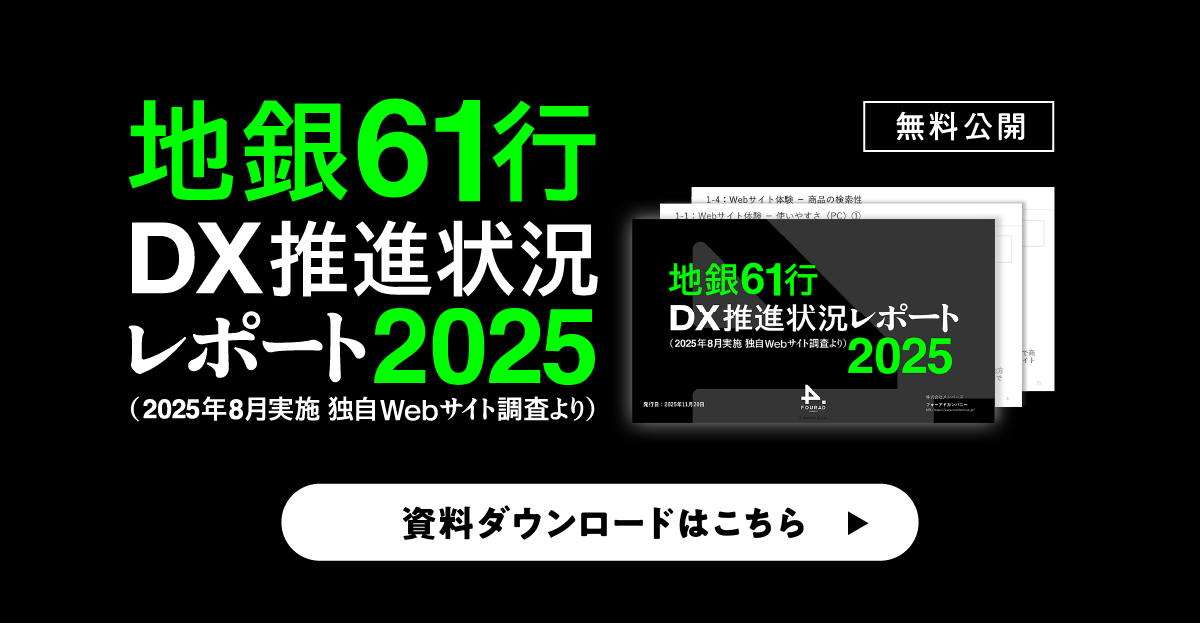避けて通れない「スマホ格差」への対応
デジタルシフトが加速するなか、地方銀行にとって“スマホに不慣れなシニア層”への対応は喫緊の課題です。ATMの撤去や窓口業務の見直しが進む一方で、オンラインサービスへの移行が進まず、利用者との“接点断絶”が起きかねない構造的リスクが生まれています。
地銀にとって、シニア層は重要な預金・資産運用の基盤顧客です。その接点を維持・進化させるには、「デジタルへの橋渡し」をいかに丁寧に設計するかが問われています。
シニア層の“つまずきポイント”とは?
操作が不安(入力、タップミス、認証手続き)
スマホの小さな文字や多層的なUI設計は、視認性や操作性に課題が多く、ミスタップや手続き途中での離脱が頻発します。
相談相手がいない
高齢の一人暮らし世帯では「聞く人がいない」ことで不安が増幅し、結果的にサービス利用を回避する傾向があります。
詐欺・セキュリティへの懸念
「スマホを使うとだまされるのでは」という漠然とした不安が、アプリやインターネットバンキング利用への抵抗感を高めています。
成功のカギは3つのデザイン視点
“学ぶ”で終わらせず、”慣れる”まで寄り添う
単発講座だけでなく、何度も聞ける・試せる「反復接点」を設計することで、体験が定着しやすくなります。
デジタル×対面のハイブリッド化
「非対面完結」を急ぐのではなく、「デジタル手続き+相談窓口」で顧客の心理的不安を段階的に解消するスタイルが有効です。
安心設計と“通知の力”
操作ログの記録や通知機能を通じて「見守り機能」を実装すれば、家族も安心。シニア本人の利用意欲にもつながります。
デジタル包摂こそ、これからの地銀価値
「使える人に合わせる」のではなく、「誰もが使えるようにする」——。それが地域の金融インフラを担う地銀にとっての本質的なDXです。
シニア層を置き去りにしない支援の積み重ねは、単なる“利用促進”ではなく、地域との信頼関係そのもの。スマホを通じた次世代接点の構築が、今まさに地銀の価値を問い直しています。